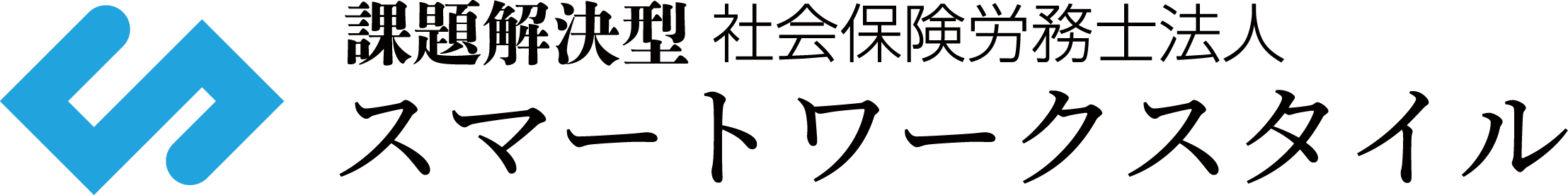異色の社労士、労働問題を科学する<第7回>
テーマ 130万円の壁問題について考える。
テーマが決まってから、既に2週間ほど筆が進まずにいます。「年収の壁」問題が非常に複雑な構造をしていることから、 どのようにお伝えするのが良いのか、 専門ではない税の問題をどの程度入れ込むべきなのか、 構成を考えだすとキリがなくなります。恐らく、 NEWS番組がこの問題を大きく取り扱ってこなかった経緯も同様なのだと思います。詳しく話し出すと場合分けが多くなりすぎて取り留めもなくなってしまいますが、 といって要約しすぎると例外が多くなりすぎて単純化した弊害が目立つようになります。この悩ましさから何度も本稿を書くことを辞めようと思ってしまいましたが、 いつもの通り私見に拘って書き上げようと決めました。異論や反論も大いにあるとは思いますが、 詳細に拘らず広い心でお読みいただければ幸いです。
『要旨』
- 「103万円の壁(税金)」引き上げで得られる減税効果により、 手取りは確かに増えることになるが、はるかに高い壁である「130万円の壁(社会保険料)」が残ることにより、 働き控えへの効果は限定的になる。
- 2026年10月に施行を目指している週20時間以上勤務労働者の社会保険加入が実現すれば、「130万円の 壁を意識しながら働く労働者は減るが、 被扶養者として健康保険料及び年金保険料を払っていなかった層の労働者の手取りは大きく減少することになる。また、 週19時間以内労働者が増える可能性もある。
- 週20時間以上勤務労働者を社会保険加入とした場合、 事業主の社会保険料の負担が確実に増える。最低賃金の大幅な上昇が継続する中で、 中小零細企業への影響は計り知れない。
- 税と社会保障の議論は、 それぞれ非常に複雑であるのに、「年収の壁」の議論を同時にした場合、 どれ程の国民がそれを我がこととして捉えられるのか疑問がある。
- 特に、 社会保険料は、 税負担とは全く違う性質のものであり、保険料負担が増えることで社会保障が 増強されることや、保険料負担の半額を事業主が負っていることを労働者に知ってもらう必要がある。
『103万円の壁問顆について』
帝国ニュ ー スでは、既に11月28日号で「103万円の壁」に対する企業アンケ ー トの記事が上がっています。引き上げに賛成と答えた企業は67.8%、撒廃すべきとした企業が21.9%でした。撒廃すべきとした企業の意見を見てみると、 「働き控えが起きやすいから」というものであったので、【壁】があることで働き控えが起きるので、 いっそう撒廃して欲しいとの見解のようです。つまり、 約9割の企業が、 労働力不足を解決するために【壁】を何とかして欲しいと考えていることが分かります。
一方、一国民としては課税所得が減ることで、 税金が減り手取りが増えることから、【壁】が何処まで上がるのかは興味のあるところです。 所得は控除の兼ね合いがあり、 家族構成によっても一律に議論出来ませんが、 課税所得があれば所得税と住民税が課せられ、 最低でも15%程度税金を支払うことから、基礎控除と給与所得控除の合計である「103万円の壁」を引き上げる議論は国民的な関心事になって当然と言えます。 ただし、「103万円の壁」を意識しながら働いている労働者にとっては、「130万円の壁」は 遥かに高い壁であることを続いて書いていこうと思います。
『130万円の壁問題について』
「130万円の壁」は、 厚生年金保険における収入の【壁】であり、 こちらは私の専門なので少し気が楽になります。 「 103万円の壁」の議論が始まって暫く経ちましたので、 NEWS番組のフリップも正確さが増しています。 恐らく社労士が監修しているのでしょう。 非常に上手くまとめられているものも増えました。 それでも、 NEWS番組の短い時間内で理解出来るのかどうか疑問があります。 まして、「103万円の壁」と同時に解説されていることも多いので尚更です。
そもそも、 130万円というのは何かということですが、 健康保険・厚生年金保険の被扶養者認定の年収 要件になります。 (※配偶者が健康保険の被保険者であるとき)
表1)130万円の壁
| 年間の見込み収入額 | 130万円未満 | 130万円以上 |
| 社会保険の加入 | 健康保険被扶養者 国民年金第3号被保険者 | 国民健康保険被保険者 国民年金第1号被保険者 |
| 保険料負担 | なし | あり |
ここで問題なのは、 保険料負担があろうがなかろうが、 社会保障としてのメリットが全く変わらない ということです。 健康保険の被扶養者でも国民健康保険の被保険者であっても、 病気になって医療機関を受診すれば、 同じように3割負担で診察を受けることが出来ます。 国民年金の第3号被保険者でも国民年金の第 1 号被保険者でも、老齢年金や障害年金の給付額に変わりがありません。 年収130万円以上になると、突然保険料の負担が増えるのですが、 とりわけ国民年金保険料(令和 6 年度 1 万6980円/月)が大きいために、 国民年金第 3 号被保険者という制度に不平等感を持つ人がいるのは仕方がないことでしょう。
『週20時間以上勤務労働者の社会保険加入』
平成27年 第 2 次安倍政権のもと「一億総活躍社会」という言葉が作られ、少子高齢化における社会の構造的な変革が求められました。「一億総活躍社会」とは、 50年後も人口 1 億人を維持し、 誰もが、 家庭で、 職場で、 地域で、 生きがいを持って、 充実した生活を送ることが出来る社会を指した言葉とのことです。 私は、 てつきり「 ー億人、 全員で働きましょう」という言葉だと思っていたので、 より深い意味があったのだと改めて感じるところがありました。 この言葉の通り、 活躍の場は家庭で、 職場でということで、 夫婦の役割分担の中で、 主に家庭で活躍する人(専業主婦・専業主夫)を健康保険の被扶養者、 国民年金第 3 号被保険者とすることは、 共働きが推奨される社会情勢であっても、「残すべき家族の形」ではないかと個人的には思っています。
ただし、年収が130万円以上になるかならないかで大きく手取りに影響する点(立憲民主党は年収の崖と呼んでいます) だけ見れば、 やはり見直しの必要性はあるのではないかと思います。 今回俎上に上がっている「週20時間以上勤務労働者の社会保険加入」という議論は、 国民年金第3号被保険者の問題を解決する一つの手段として非常に重要です。
表2)週20時間勤務の壁
| 年間の見込み収入額 | 130万円未満 | (1040時間X時給)以上 |
| 社会保険の加入 | 健康保険被扶養者 国民年金第3号被保険者 | 健康保険被保険者 厚生年金被保険者 |
| 保険料負担 | なし | あり |
年間の見込み収入額は、(1040時間X時給) 以上としていますが、 1040 = 20(時間)X52(週)、 つまり1年間の労働時間が1040時間以上になる働き方なら厚生年金保険に加入しなくてはいけなくなるということです。もし、栃木県の最低賃金である時給1004円なら年収104万4160円で厚生年金保険に加入することになります。
では、年収130万円未満の国民年金第3号被保険者と、年収104万4160円以上の厚生年金被保険者では、どちらが優先されるのでしょう? これは、 厚生年金被保険者が優先されます。 つまり、 社会保険の壁が130万円から105万円に下がったことを意味します。
ただし、 表 l と表2 の壁で決定的に違うのは、 保険料の負担に相応した社会保障が得られるという点です。
表3)国保・国年と健保・厚年の違い
| 社会保険の加入 | 健康保険被扶養者 国民年金第3号被保険者 | 健康保険被保険者 厚生年金被保険者 |
| 出産時保険料 | 元々保険料負担なし | 免除される |
| 出産手当金 | なし | あり |
| 傷病手当金 | なし | あり |
| 老齢年金 | 上乗せなし | 上乗せあり |
| 障害年金 | 2級から、 基礎のみ | 3級から、 基礎+厚生 |
| 遺族年金 | 上乗せなし | 上乗せあり |
健康保険の被保険者かつ厚生年金の被保険者であることが、 如何に社会保障上のメリットが大きいかを訴えたNEWS番組を見たことがありません。 週20時間以上勤務労働者の社会保険加入を議論するときには、 是非ともこの視点 、 つまり「払い損ではなく、 保障は大きいよ」ということをしつかり伝えて欲しいと思っています。
『まとめ』
今回、 年収の壁という非常に困難なテ ー マに挑んでみました。「103万円の壁」という税金の壁は、 突き詰めると所得控除に関する知識が必要となります。 このような議論が起きているときがチャンスだと思って、改めて任意保険の加入状況やiDeCo、ふるさと納税など見直しを行ってみると良いと思います。一方、「130万円の壁」は健康保険の被扶養者(国民年金第3号被保険者)の認定が外れるかどうかで、手取りへの影響が甚大であることから、国民一 一人がもっと興味をもって頂かなくてはならない【壁】です。今回提示した「週20時間以上勤務労働者の社会保険加入」という選択や、 日本商工会議所や労働組合連合、 経済同友会が主張する 「国民年金第3号被保険者の廃止」という議論も労働者の生活を大きく変える可能性があることから注目していかなくてはなりません。そして、 何よりも重要なのは、 社会 保険はどんな時に給付があるのか知ることです。社会保険は申請制なので、 何かが起きていても申請しなければそれつきりです。給付されません。
表4)税金と社会保険料の違い
| 使途 | 使途の決定 | 給付 | |
| 税金 | 公共サービスなど | 納税者に決定権なし | 原則、自動 |
| 社会保険料 | 特定の社会保障 | 法律の定めあり | 原則、申請 |
最後に、 これからは間違いなく社会保険の加入範囲は拡大します。これは最低賃金が上昇することと同時に起きます。最も影響を受けるのは中小零細の事業主で間違いありません。特に重要なのは、「福利厚生を高めて働きやすい職場を醸成し、良質な労働者が定着する会社を作ることです。」企業は人なりです。お金をかけずに出来る福利厚生もあります。広義の社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)を最大限活用して下さい。私は同じ立場の事業主として、 この流れに乗っていくための情報提供を行っていきたいと思います。
本稿が、 少しでも皆様の事業の発展に寄与出来れば幸いです。
〈著者プロフィール〉
オフィス スマートワークスタイル 代表 社会保険労務士 下田 明範
[略歴]
<1974年>
3月27日生(50歳) 埼玉県上福岡市(現ふじみの市)出身
<1997年>
東京理科大学薬学部卒業 薬剤師免許取得
同年から17年間武田薬品工業(株)のMRとして大学・大病院を担当
<2016年>
栃木市にそらいろ調剤薬局を開業(2024年4月現在栃木市3店舗・小山市1店舗)
<2022年>
オフィス スマートワークスタイルを開業 (2024年4月現在社労士4名・事務員2名在籍)
<2023年>
栃木県社会保険労務士会 理事就任
<2024年>
社会福祉士通信課程(一般)に入学
年金マスターとして週1回年金事務所に勤務障害者雇用管理サポーター登録
[趣 味]
楽天ポイントの貯まるお買い物