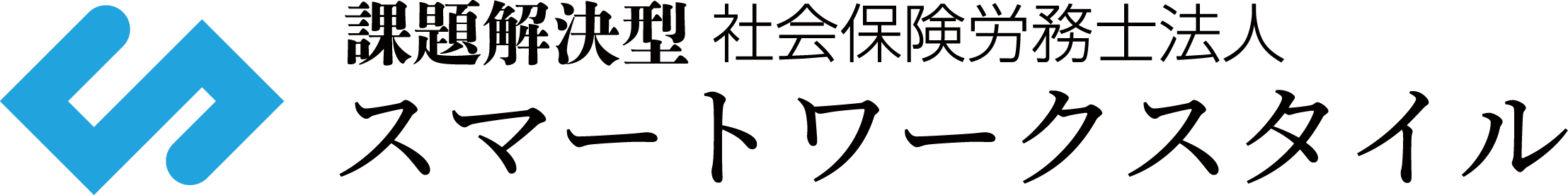雇用管理システム構築

雇用管理システム構築で、
法的リスクを減らしつつ、効率的な管理ができる体制を。
変形労働制など多様な働き方の導入に関する支援を行ないます。労働力を最適化するために必要な労働時間管理を実践に基づいて提案します。
労働生産性を基軸とした賃金規程の作成を支援いたします。顧問契約時には賃金計算を承ることも出来ます。
開業時から係ることが出来る場合、最適な雇用管理システムを提案することは比較的容易ですが、既に事業が継続する中でシステム変更することは大変難しく、多大な労力が必要となります。しかし、今始めなければ数年後も同じ問題を抱えることになります。最適な雇用管理システムを共に模索させて下さい。
このような方は是非ご相談ください
労働条件、労働時間、給与の計算方法をシステムで管理したい。
労働時間や残業時間の自動計算機能を構築したい。
社会保険料や労働保険料の計算を自動化したい。
従業員の出勤状況・休暇申請・残業時間などを一目で確認できるようにしたい。
法令遵守のチェック機能を組み込みたい。
人事データ(住所、給与、勤怠、保険加入情報等)を統合管理したい。
どの助成金が適用可能かをシステムで自動判定させたい。
依頼時の流れ
ニーズのヒアリング
現在の雇用管理状況、問題点、改善したい点を社労士に伝え、どのような機能が必要かを明確にします。
システム設計とアドバイス
ニーズに合わせたシステム設計を行い、法的な要件を満たすようにします。システム開発会社と連携して、具体的な仕様を決定します。
システム開発と実装
開発段階で法的アドバイスを提供し、システムが法的に正しく設計されるようサポートします。
テストと運用開始
システムの運用を開始する前に、テストを実施し、実際の運用において問題がないか確認します。
運用後のサポート
システムが運用開始された後も、労務管理に関するアドバイスや法改正に対応した調整が必要な場合、引き続き社労士がサポートします。
お問い合わせ・無料相談はこちらから
取り扱い領域
雇用契約書・就業規則の整備
労働時間・残業時間の管理
給与計算・社会保険料の管理
休暇・有給休暇の管理
人事データ・従業員情報の管理
法令遵守の管理機能
助成金の申請・管理
従業員の福利厚生管理
セキュリティとデータ保護
システム導入後の運用サポート
実績
会社設立に伴う労働保険成立及び社会保険の新規適用手続
入退社による資格取得・喪失手続
扶養家族の変更による被扶養者異動手続
女性従業員の妊娠・出産・育児・復帰に伴う手続全般
男性従業員の育児・復帰に伴う手続全般
支店設立に伴う労働保険継続事業一括申請手続及び雇用保険非該当承認申請手続
会社の移転や社名変更に伴う所在地変更及び名称変更手続
会社の全国健康保険協会から健康保険組合への編入手続
各種労使協定の作成・届出手続
就業規則・諸規程の作成・届出手続
年金事務所の調査対応
労働基準監督署の調査対応
よくある質問
雇用管理システムの構築にかかる期間はどのくらいですか?
システム構築にかかる期間は、企業の規模やニーズによって異なります。一般的には、ニーズのヒアリングから設計、開発、テスト、導入までに3ヶ月から半年程度かかることが多いです。しかし、急ぎの対応が必要な場合や、シンプルなシステムの場合は、短期間での対応も可能です。どのような機能をシステムに組み込むことができますか?
システムには、以下のような機能を組み込むことができます。○労働時間や残業の管理
○給与計算と社会保険料の自動計算
○暇や有給休暇の管理
○勤怠データの集計とレポート作成
○雇用契約書や就業規則の管理
○助成金の申請サポート
○法令遵守チェック機能 など
○企業の特定のニーズに応じて、カスタマイズや追加機能を加えることも可能です。