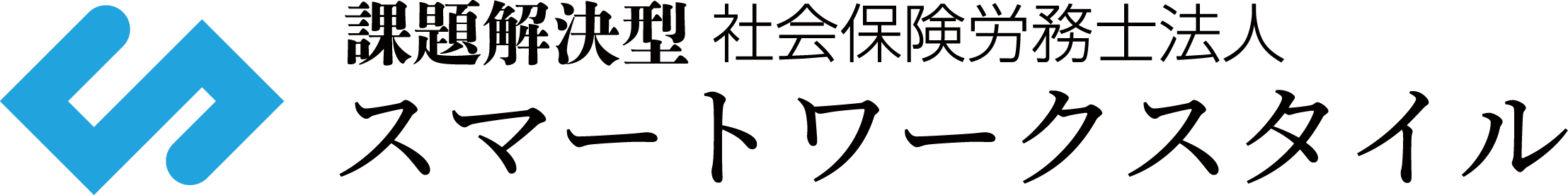異色の社労士、労働問題を科学する<第1回>
『はじめまして』
この度、帝国データバンクさんのご厚意で、こちらにコラムを連載させていただくことになりました。数年前から、毎晩のようにプライムニュースを見ながらブツブツ言っていて、付き合わされる家内も段々といい加減な相槌を打つようになっていたことから、このような機会をいただけたことで、私の周りの人たちもベクトルがほかの方向に向かうと喜んでくれるのではないかと思っています。
初寄稿となる今回は、私の経歴や現状について紹介させていただきながら、私の考え方のバックグランドに何があるのか感じ取ってもらえればと思っております。また、次回以降のテーマについても予告したいと思います。
『大学卒業から薬局を開業するまで』
大学卒業後、製薬会社のMR(医薬品の営業のこと)となり、約17年間営業一筋のサラリーマン生活を送っておりました。転機となったのは、家内の「一生転勤する生活より、ここで一緒に薬剤師をする方がいい」という希望でした。出世レースの真っただ中でもあり、今までの努力を棒に振ることになる転職など眼中にもなかったのですが、魔がさしたというか、ある日突然転職に向けて行動を起こし、そこそこ順調だった出世レースから降りてしまいました。幸い、そのときどきの状況に対して後ろ向きに捉えることのない性格であり、まして自分で決めたことなので、全力で転職先を探した結果、「営業職兼 薬剤師」という特殊な待遇での転職が叶い悲惨な収入減とならずに済みました。薬局の運営について学び、3年後に図らずも独立することになり、小さい会社ながらも代表取締役という肩書を持つことになりました。
『異色といえば異色』 実は、ここまでは業界的にはよくある話です。営業力のあるMRが薬局を起業すると、かなりのスピードで勢力を拡大するというのが定番となっていました。しかし、薬局の経営はひと時の隆盛は過ぎており、コンビニより多いと椰楡されるほど飽和状態に入っています。そのような環境下で、ただひたすら店舗展開のために営業活動を行うのは、MR時代と本質的に何も変わらないことは分かっていたので、何か違うコンセプトで会社を運営してみようと思ったのが社労士への入り口でした。つまり、「大きな会社にする」という対外的な評価を商める努力ではなく、労働者にとって魅力的な会社を作るという方法で人を集め、結果として安定的に成長できる企業にすることを目指すことにしました。そのためには、労働基準法や社会保険について学ぶ必要がありました。お恥ずかしい話、40歳で転職するまで「国民年金」と「厚生年金」の違いすら知らなかったのです。自分の無知を克服しようとしたら、その延長線上に社労士資格の取得があっただけで、本人的には全く違和感がないのですが、「薬剤師が社労士を取得する」ということ自体、確かに異色といえば異色ですね。
『科学するとは』
私は昔から「科学する」という言葉が好きで頻繁に使ってきました。「科学とは、一定の目的・方法の下でさまざまな現象を研究する認識活動、およびそこからの体系的知識。」だそうです。私が使う「科学する」という言葉も同義ですが、簡単な言葉に置き換えると、ある事象を 調査し、分解し、分析し、比較し、分類し、試し、評価し、実践し あらゆる手段を用いて、合理的な方法を導き出す過程のことを総称しています。ただ誤解されたくないのは、「科学=理系」的な敷居の高いイメージを持たないで頂きたいのと、私が手段として用いる方法は、あくまで中学生くらいまでに学んだ知識を使用しており、決して特有な言い回しや理論、難解な横文字を使用することはないということです。そして内容はほぼ実践に基づいていることから、「論理的には」とか「理想的には」ということもありません。科学するこ とで最適解を導き出すのですが、最終的にはその最適解に向かって環境を変化させなければなりません。ここが正に事業主の腕の見せ所です。固定概念を打破することは本当に困難なことです。ー朝ータには出来ません。時間がかかることを覚悟し、「変化」を受け入れる素地を会社全体に醸成することから始めなくてはなりません。ただし、今始めなければ10年後も今のままであることは間違いないのです。私の経験では、「変化」を受け入れやすいのは業績が良いときです。今はそのときでしょうか?
『3つの視点を持つ』
私が物事を科学するときに特に気を付けていることは、視点を大切にするということです。ひとつの事柄に対して、事業主として見る場合と、労働者として見る場合では、全く違う見え方になるということは想像に難くないと思います。視点を多く持てば、より正確に物事を把握できるのではないかと考えています。プロフィールにも書いてありますが、株式会社アポニーズという会社の「事業主」であり、オフィス スマートワークスタイルという会社で「労務の専門家」として活動しています。さらに、「労働者」の視点を忘れないように、日本年金機構から委嘱された年金事務所での窓口業務を週に1回行っています。実は、私は3つの仕事の中でこの仕事が一番きついです。確かに、労働者には経営的なプレッシャーは殆どないのかもしれませんが、業務に対する責任というプレッシャーは十分にあることが分かります。その重みを常に意識しながら雇用をしているので、従業員に心から感謝できますし、何らかの行動を起こすときに「労働者」として考えた場合という視点を何時でも持っていられます。勿論、皆さんに同じようなことを求めている訳ではありません。私が労働問題を科学するうえで、「労働者」の視点も加味しているということを申し添えたかっただけです。これは意外と重要な要素かもしれません。
『労働問題として取り上げる題材について』
直近では「2024問題」がメデイアに頻繁に取り上げられていると思います。簡単に言うと、「残業の規制が他の一般業種並みになりますよ。」ということですが、これは単に残業の問題ということだけでな く、採用や継続雇用、給与システム、労務管理といった雇用管理全般と一体になっている問題です。業種特有の問題が多分に含まれているので、一概にこうした方が良いとは言い難い状況がありますし、提案しても事業主さんにそのまま受け入れられることはありません。私がこの「2024問題」に対して申し上げたいのは、小手先でその場限りの対策をしても、長期に安定した事業の発展はあり得ませんよということです。この問題を契機に、抜本的に雇用管理を見直さないといけないというのが私の見解です。
『科学するとは』の項でも申し上げましたが、固定概念を打ち破り、「変化」を受け入れなくてはいけないと思います。急激に「変化」を受け入れることは難しいですが、最適解に向けて地道な努力をしていけば、10年後には全く違う企業になっているのではないかと思います。次回はトピックスである業務改善助成金について解説したいと思いますが、それ以降は、企業ごとに労務管理上の最適解を導き出すためのヒントをご提供していきたいと思います。その内容は、「3つの視点」をもって私なりに科学した結果です。私のメイン業務は調剤薬局と社労士事務所なので、殆どの事業主さんとは業種が違うことになると思いますが、必ず学びはあると思います。感性を研ぎ澄まし、是非自分たちの会社ではどのように活用できるかを考えて頂ければ幸いです。
他にも、「業務改善助成金以外の助成金の活用方法」・「短時間バイトの問題」・「人材不足と採用の問題」・「社会保険加入の問題」・「多様な人材の活用方法」など事業を安定化するために役立つであろう情報や考え方を綴っていきたいと思います。今後とも宜しくお願いします。
〈著者プロフィール〉
オフィス スマートワークスタイル 代表 社会保険労務士 下田 明範
[略歴]
<1974年>
3月27日生(50歳) 埼玉県上福岡市(現ふじみの市)出身
<1997年>
東京理科大学薬学部卒業 薬剤師免許取得
同年から17年間武田薬品工業(株)のMRとして大学・大病院を担当
<2016年>
栃木市にそらいろ調剤薬局を開業(2024年4月現在栃木市3店舗・小山市1店舗)
<2022年>
オフィス スマートワークスタイルを開業 (2024年4月現在社労士4名・事務員2名在籍)
<2023年>
栃木県社会保険労務士会 理事就任
<2024年>
社会福祉士通信課程(一般)に入学
年金マスターとして週1回年金事務所に勤務障害者雇用管理サポーター登録
[趣 味]
楽天ポイントの貯まるお買い物