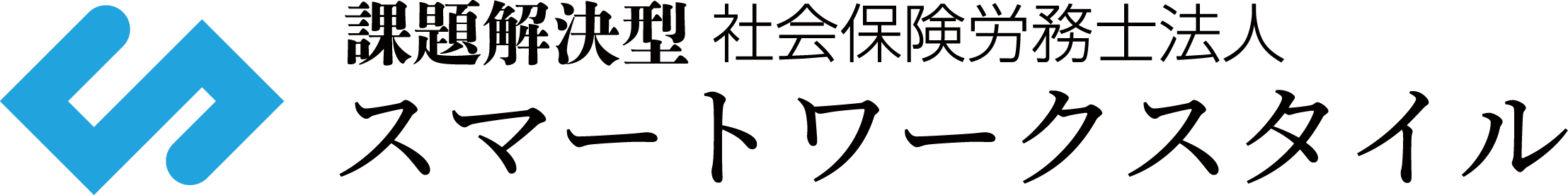異色の社労士、労働問題を科学する<第5回>
今回は今話題になっている労働問題について考えていきたいと思います。
『労働力の流動化とリスキリング』
私はこの原稿を、 自由民主党の総裁選挙及び立憲民主党の代表選挙の真最中に書いています。 ある候補者がタイトルのように、 労働力の流動性を高めることによって賃金を上昇させるということを言っておられます。 理屈は下記の通りです。
労働力の流動性を高める
↓
有望な職種や職場に労働力が集まる
↓
労働力獲得のための競争が激化する
↓
賃金は上昇する
当然、 そのためには労働者の方も有望な職種や職場に見合った能力を有していなくてはなりません。そこで、 流行語のリスキリング(Re-Skilling :学び直し)が登場します。
さて、 ここで私の疑問です。 周りを見回して、 リスキリングしている人ってどの程度いらっしゃいま すか? 労働人口が集中し、 大学も多い大都市圏では、 リスキリングが流行っているのかもしれませんが、 果たして地方都市でも同じことが期待できるのでしょうか? 少なくとも栃木市にはものすごい数 の学習塾はあるものの、 大人向けの塾はなさそうです。 では、 事業主の皆さんが労働力の流動性を高めるために、 労働者にリスキリングを勧めるのかということですが、 ちょっと考えにくいですよね。
つまり、 大都市圏で働く一部のホワイトカラーでは、 労働力の流動性を高めることで賃金上昇が期待できるかもしれませんが、 地方都市には馴染まないし、 むしろ悪影響の方が強いと私は考えています。
『労働力の流動化のマイナス面』
最初に断っておきますが、 労働力の流動化を否定している訳ではありません。 むしろ可能性への挑戦 や社会の変化への対応といった意味で、 そういった視点を持てる人には、 是非とも頑張って欲しいと願っています。 が、 賃金を上昇させるための起爆剤として、 労働力の流動性を高めようとすることは、その流れに乗れない人に対してあまりにも無責任ではないかと思っています。 私達の年代なら視たことなくても名前は知っている「ハケンの品格 (2007年)」というドラマがありました。 色々な資格を有して、 あらゆることに対応可能な派遣労働者を篠原涼子さんが演じていました。 当時増加の一途であった派遣労働者の地位向上のために企画されたドラマなのかもしれませんが、 1999年に24.9%であった非正規雇用率が2023年には37.1%になっています。 福利厚生の面で有利な正規雇用の割合が減っていること は由々しき問題です。 もし、 安易に、 転職により収入がアップするという都合の良い情報を信じて、 今 の職場を離れてしまったらと考えると、社会保険の専門家として憂慮せざるを得ません。
『労働問題のかみ合わない議論』
一方、 立憲民主党は、 弱者切り捨てになると一貫して上記の施策を否定しています。 私も、 なぜ労働カの流動性を高めるために解雇制限の緩和が必要なのか理解出来ていません。そもそも、 どちらの主張が正しいとかではないなと思いながらTVを見ています。なぜなら、主張している視点が違うからです。
A.自由民主党の一部候補者の主張
解雇制限を緩和 労働力の流動化 リスキリングの推奨
B.立憲民主党の主張
雇用規制の維持 正規雇用率の上昇 リスキリングの推奨
さて、 Aの主張は、 日本の国力増大を目標に、 グロ ーバル化やイノベー ションを促進させるために必要な項目です。 しかし、 国民全員が仕事を中心に生きている訳ではありません。それを公約のように話し出すと、 あたかも転職すると賃金も増えて良いことだらけのように映ってしまうのではないかと懸念してしまいます。 後述しますが、 転職のリスクをもっと重大に捉えて頂かないといけないのです。
一方、 Bの主張は、 国民生活の安定を念頭にセー フティ ー ネットの強化を謳っています。 ただし、 事業主への負担を強いるものですから、 現状で安定している事業主にとっては利益確保が難しくなるので はないかと思います。
つまり、 Aは国を豊かにして国民生活を良くしていくというトリクルダウン的な視点で、 Bは職業を 安定化することで国民生活を良くしていくというボトムアップ型の視点で、 雇用の問題を議論しているのですが、 全く違う層の労働者を意識して話をしているので、 かみ合うはずもありません。
『あくまで、 個人的な意見』
Aの施策は、 将来に向けリスキリングを行い、 習得後はもっと良い条件の企業に再就職するという目標を持つ人を支援すれば良いのですから、 ことさら新しい法律を作り、 規制緩和をする必要はありません。 なぜなら、 既にハイクラス転職などで民間企業が活発に動いていますし、 そういった層の人たちは 自らリスキリングも行っています。 もし、 国がこういった人たちの背中を押せるとしたら、 夢破れた時 にしっかり支えてあげられる仕組みを作ることです。 そうすれば、 もっとチャレンジする人が増えて、 労働力の流動化による賃金上昇という目標が達成されるのではないかと思います。
一方、 このような流れと無関係な人に関しては、 Bの主張のように、 正規雇用率が上がるような施策を徹底して行う必要があります。 私は、 年金事務所に週1回勤務して年金の請求を受け付けていますので、 年金記録と年金の試算額を見ます。 そこで、 厚生年金の被保険者として働くことの重要性を肌で感じています。 若いときには分かりにくいのですが、 雇用の安定が老後の安心を生むことはれっきとした事実です。 遣りたいことを追い求めての結果なら、 自らの責任ということになるのでしょうが、 国が転 職を勧めた結果として就労期間が短くなったとしたら、 目も当てられません。
『まとめ』
今回は、労働者目線で、今話題の労働問題を考えてみました。故に、どちらかというと立憲民主党寄りの内容になっていると思います。どの視点で問題を見るかによって捉え方が変わるのですが、忘れてはいけないのは、事業主にとって労働者は、自らの事業に、もっと言えば、夢を叶えるために力を貸してくれる存在です。給与や賞与といった直接的な待遇で報いることは勿論のこと、労働者の視点で労働問題を考えることは、日頃の感謝を伝える手段にもなり得るのです。綺麗事のように感じられる事業主 の方もいらっしゃると思いますが、労働者の定着が如何に重要であるかは次回以降に例示していきます。また、《働き方改革》の実務的な利用方法も触れていこうと思います。本稿が、少しでも皆様の事業 の発展に寄与出来れば幸いです。
〈著者プロフィール〉
オフィス スマートワークスタイル 代表 社会保険労務士 下田 明範
[略歴]
<1974年>
3月27日生(50歳) 埼玉県上福岡市(現ふじみの市)出身
<1997年>
東京理科大学薬学部卒業 薬剤師免許取得
同年から17年間武田薬品工業(株)のMRとして大学・大病院を担当
<2016年>
栃木市にそらいろ調剤薬局を開業(2024年4月現在栃木市3店舗・小山市1店舗)
<2022年>
オフィス スマートワークスタイルを開業 (2024年4月現在社労士4名・事務員2名在籍)
<2023年>
栃木県社会保険労務士会 理事就任
<2024年>
社会福祉士通信課程(一般)に入学
年金マスターとして週1回年金事務所に勤務障害者雇用管理サポーター登録
[趣 味]
楽天ポイントの貯まるお買い物